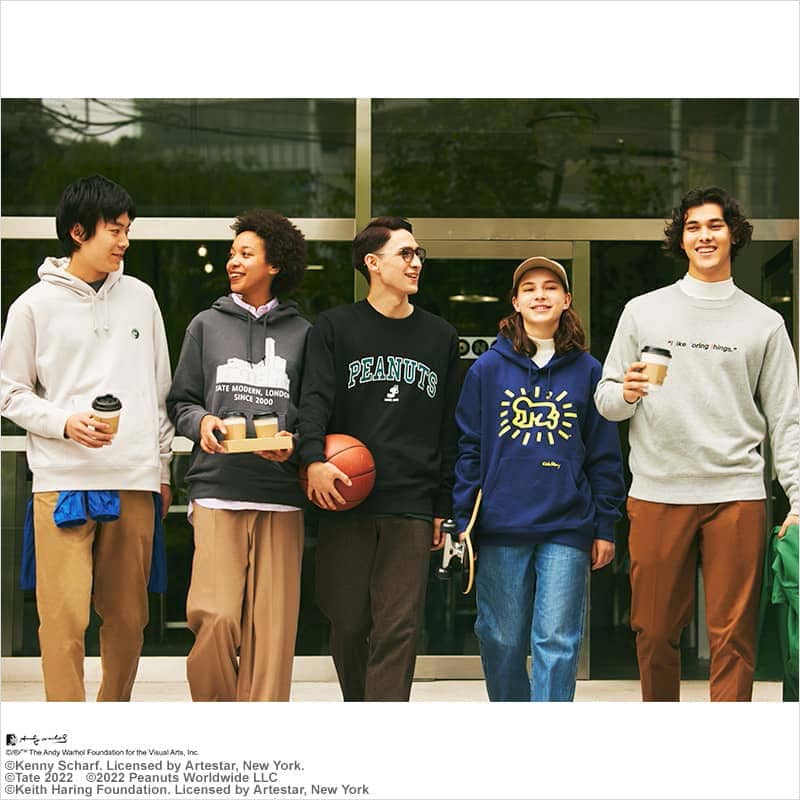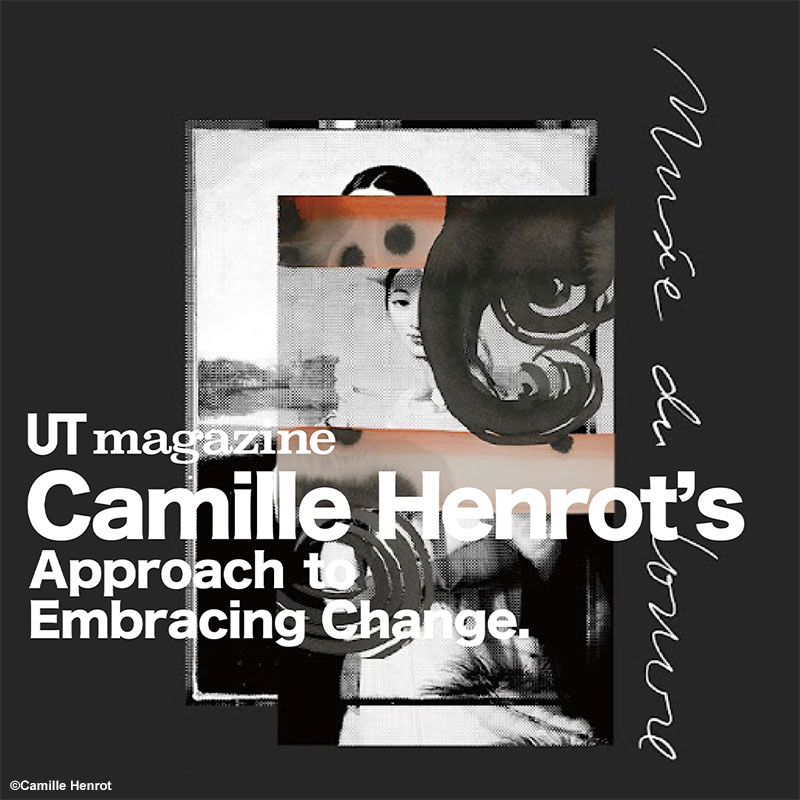1960年代より日本のみならず世界中の路上を放浪しながら、スナップショットの可能性を追求してきた写真家の森山大道さん。代表作である通称『三沢の犬』をはじめ、今回UTになった作品をとおして、森山さんの写真に対する思いを語ってもらった。
選んで着てくれた人を見かけたら嬉しいんです。
「単純に嬉しい」。写真家(本人としてはカメラマンという肩書のほうがしっくりくるそうだが)の森山大道さんは、自身の作品がUTのTシャツになることに対してそう語る。孤高の作家というイメージがある森山さんだけに、このストレートな反応には少し驚いた。
「ぼくはギャラリーで額に入った写真展をやるよりも、Tシャツとか時計にしてもらえるほうが嬉しいんです。Tシャツになった作品は、ぼくがよく撮る街角の看板や映画館のポスターと一緒。着る人は作者のことなんて考えない。それがいいんです。だから、選んで着てくれた人を見かけたら嬉しい。声をかけて握手したいくらい。それは冗談ですけど(笑)」

今回のUTの中で、森山さんがもっとも気に入っているのは、『手』のTシャツだそう。
作品が作者から離れて広まることを夢見る。それは、署名なしでも見る者の心を揺さぶる、唯一無二の強い作風を築き上げてきたからこそ言えることなのかもしれない。例えば、今回のラインナップのなかでもっとも古い作品である『三沢の犬』を見れば、その強さは誰の目にも明らかだろう。1971年に青森県の米軍基地の街と知られる三沢で撮られた、森山さんの代表作である。
「当時、雑誌『アサヒカメラ』で『何かへの旅』という連載を持っていて、三沢へはそこに載せる写真を撮るために行きました。ぼくは横須賀とか、基地の街の雰囲気が好きだったから。そんなある朝、ホテルから出た瞬間に目の前にいたのが、この犬。たぶん米軍の兵隊が捨てていった野良犬だとぼくは勝手に思い込んでいるんだけど、胡散臭い顔して、じろっとこっちを睨みつけてきたんです。それでパパっと2、3枚撮って、帰ってプリントするときに拡大してみたら、なかなかの表情だったんですよ。『おぬし、やるな』って感じで(笑)。それで雑誌に見開きで載せたら、みんなが面白がってくれて、ニューヨークの『MoMA』を始め外国からも声がかかるようになった。たぶんぼくの撮った中で一番世界を回っているんじゃないですかね」
この『三沢の犬』は、森山さん自身のセルフポートレートと評されもする。路上をうろつきながら鋭い眼差しで世界を見つめる野良犬の姿が、カメラを構える森山さんに似ているからだ。そのことに対して、本人はどう思っているのだろうか。
「撮っている本人はそんなことは思わないけど、どこに行ってもすぐ街角に入っちゃって落ち着きがないから、『あいつ野良犬みたいだな』とはよく言われる。だから、そういう感じはどこかにあるんでしょうね」

これがオリジナルの『三沢の犬』。「ぼくの場合、現場では何気なく撮ったものでも、現像したときに驚いて、“作品”にすることが多い。これは特にそれを感じた一枚」と森山さん。

『三沢の犬』は今回のUT以外でもいろいろグッズ化されている。ポストカードだろうか。
写真というのはすべて世界の破片なんです。
ところで、『三沢の犬』のオリジナルは、犬の全身が写っている。今回のTシャツではそれを大胆にトリミングしているが、こうした改変に対しても寛容なのは、森山さんならではの写真観が影響しているようだ。
何をどう切ってもいいとは必ずしも思わないけど、そもそもこの犬ももっと遠くから撮ったものを、現像の時点でトリミングしていますからね。写真っていうのはすべて世界の破片なんですよ。いくらワイドで撮ったところで、破片しか写らない。ぼくはそういうふうに思うタイプだから、トリミングしたっていいじゃないと思う」
写真家になる以前、森山さんはデザイナーをやっていたことで知られる。そのときの経験が、トリミングへの寛容さにつながっているなんてことはあるんだろうか。
「それはあると思う。昔は思わなかったけど、ずっと後になってそう考えるようになりました。デザインといったってかじった程度で、ぼくには合わなかったからすぐ辞めてしまったんだけど、そのスタジオに外国の雑誌や写真集がいっぱいあって、ぼくはそれを見ていたんです。そこで見たものの印象が、体に染み付いちゃっているんでしょうね。だから、好き勝手にトリミングしてみたりするんだと思う。あと影響ということでいえば、ウィリアム・クラインの写真集『ニューヨーク』(1956年刊行)が、多少はあるかもしれません。クラインはぼくよりももっと大胆にトリミングしていますから。『ここまでやるか?』ってものもあるけど、やっちゃいけない理由はどこにもない。そのフリーな気持ちが、ぼくはいいなと思えた。だから、『ニューヨーク』はぼくにとってある種のバイブルです」
どの街を撮っても基本は変わらない。 自分の欲望と街の欲望が交差した瞬間に撮る。
ニューヨークといえば、今回のコレクションの中には、この街を写した作品もラインナップされている。『三沢の犬』と同時期、美術家の横尾忠則さんに誘われて初めて訪れたときに撮った『NY』だ。しかし、日本にいようと外国にいようと、街にカメラを向ける姿勢に大きな違いはないという。
「どこにいても一緒です。とにかく1枚でも多くのスナップを撮りたいっていうだけ。人がいる街があれば、そこに分け入る。そこで自分の欲望と街の欲望が交差した瞬間に撮るっていうのが、ぼくのスナップの基本ですから。それは東京でもニューヨークでも変わらない。もちろん、風景が変われば少しは変わるとは思うけど、ぼくはあんまりそういうことは考えないんですよ。土地の固有性みたいなものにも、ほとんど興味がないから。ちょっと違うのは、遠野を撮った『遠野物語』くらい。それ以外は、どこを撮っても姿勢に変化はありません。国道を撮っていたときだって、東京が細長くなっただけだと思っていたくらいですから(笑)」
もちろん、その姿勢は『Paris』についても当てはまる。しかし、「パリはあんまり写真が撮れる場所じゃないんですよ」とつぶやく森山さんは、「だって、もうアジェがいるから」と付け加える。アジェとは、19世紀後半から20世紀前半のパリを撮り続けた、写真家のウジェーヌ・アジェのことである。
「どこを撮ったってアジェみたいになってしまう。パリは変わっているところもいろいろあるんだろうけど、古い建物が多く残っているから、ちょっと脇道に入るともうアジェ。あれだけ世紀末のパリを撮りまくっていたその欲望は、やっぱり半端じゃない。それでも写真集にしてもらったものは、アジェとは違うものが撮れたかなってものですけど。自分なりにね」

‘80年代後半から数年間、森山さんは自身のプライベートギャラリーを作るべくパリと東京を往復していた。最終的に計画は頓挫したが、『パリ』はそのときに路上で撮った作品で、写真集『パリ+』としてまとめられた。
自分自身でも街でも ぱっと見て面白かったら、一瞬で撮る。
どこにいても、街を行き交う見知らぬ人影にカメラを向ける姿勢に変わりはない。では、自分が被写体になるときはどうなのだろうか。森山さんは、自身の体の一部や影、あるいは鏡に映り込んだ姿を、しばしば写真に収めている。今回のコレクションでいえば、『手』や『影』のような作品だ。
「それも変わらないです。『あいつ、自分ばっか撮って』って言われるんだけど、そういうつもりじゃない。ただ、ぱっと見て面白かったら、一瞬で撮る。『手』だって、池袋の仕事場のベランダにいたら、向こうに新宿の街並みが見えたから撮っただけ。そういう意味ではね、ぼくの写真ってあんまり深い意味はないんですよ。目の前に今あるもの、これから会えるかもしれないものに興味を持っているだけで。だから、ぼくが街を歩いているときは、本当につんのめるというか、先のことばかり見ている。それでとにかく全部撮っているつもりなんですよ。もちろん、実際にそうはいかない。いっぱい見落としているはずだから。だけど、自分では全部撮っているくらいの気持ちでやっているんです。」
『手』の向こう側に写る新宿は、森山さんがもっとも多くのシャッターを切った場所として知られる。そこまでこの街に惹かれる理由は何なのだろうか。
「ぼくの性格と新宿のそれが似ているんでしょうね。こう言っちゃ悪いけど、いかがわしいところとかね。だから、閑静な住宅街に行っても何も面白くない。2年くらい前にある街へ行ったときは、1枚しか撮れませんでしたから。それも無理して撮ったものです(笑)。いろいろな街へ行っても、結局は新宿に戻ってきてしまうんです。『飽きませんか?』ってよく聞かれるけど、飽きてないこともない(笑)。でも、しょうがないじゃないですか、目の前に新宿があるんだから。初めて大阪から上京して来て、新宿の東口に降り立ったときから、ずっとそんな気持ちがあるんです」

『手』は、森山さんの畏友でもある寺山修司のエッセイ集『スポーツ版裏町人生』をイメージして編集された写真集『Daido Moriyama Terayama』に収録。森山さんが手を新宿の風景にかざしている構図が印象的だ。
森山さんが新宿を撮り始めた時代から比べれば、その姿はずいぶんと変わったことだろう。しかし、そうしたことに対するノスタルジーは、森山さんからこれっぽっちも感じられない。
「もちろん、変わっていますよ。新宿だけじゃなく池袋もそうだし、渋谷なんて信じられないくらい変わってしまいました。でも、そんなこと言ったってしかたないじゃないですか。写真には今しか写らないんだから。そしたら今の姿を写すしかない。駄目と思えたって、写さないほうがもっと駄目だとぼくは思っているんです」
生き物のような街とそこに行き交う人々の“今”を記録するため、今日も森山さんは外に出てシャッターを切る。そうした姿勢は、コロナで人々の生活が激変して以降も変わらないという。
「最初の緊急事態宣言のときは、2日は家にいたけど、3日目からは街に出ました。だって、撮るしかないじゃないですか。こっちはリモートワークなんてできないんですから。もちろん、人は少なくなっていました。でも、いなきゃいないでいいじゃないですか。それが今なんだから」

ぷかぷかとタバコをくゆらす森山さん。その姿はハードボイルドな存在感を湛えていた。この日の森山さんは、かつて自身が仲間と新宿二丁目で運営していたギャラリー「CAMP」の復刻版Tシャツを着ていた。

(犬 Tシャツ)
殺気立った野良犬の表情を含め、一度見たら忘れられない『三沢の犬』。Tシャツではトリミングによって、その表情が強調されている。

(手 Tシャツ)
何十年にもわたって街でカメラを構えてきた森山さんの手が写った一枚。いわく、「撮ったのは20年近く前なので、まだ手が若い(笑)」

(パリ Tシャツ)
今回のTシャツにはすべて、森山さんの直筆サインのプリントが施されている。他は袖だが、『パリ』では胸元に。

(NY Tシャツ)
『NY』のTシャツは写真のネガを使用。その下には、同作が収録された写真集のタイトル『’71-NY』の文字もプリントされている。

(影 Tシャツ)
海辺に砂浜に打ち捨てられたタイヤとそこに差し込む森山さん自身の影を写した『影』。ただ、森山さんは撮った記憶は残っているが、撮影した場所を覚えてないという。
PROFILE
もりやま・だいどう|1938年、大阪府生まれ。岩宮武二、細江英公の助手を経て、64年にフリーの写真家に。日本のみならず世界各国で展覧会を開催している。主な写真集に『にっぽん劇場写真帖』『写真よさようなら』『記録』シリーズなど。
©Daido Moriyama Photo Foundation
※店舗ごとに在庫状況が異なりますので、予めご了承ください。
※UTの全ての商品ラインナップが揃う店舗は、「オンラインストア」と下記の「UTフルラインナップ店舗」です。
原宿店、ユニクロ TOKYO、ユニクロ PARK 横浜ベイサイド店、銀座店、ビックロ ユニクロ 新宿東口店、渋谷道玄坂店、御徒町店、池袋サンシャイン60通り店、世田谷千歳台店、吉祥寺店、札幌エスタ店、名古屋店、京都河原町店、心斎橋店、OSAKA店、あべのキューズモール店、イオンモール沖縄ライカム店